

(結論)学習プランによっておすすめの順番が2つあります。
最短合格をめざすならパート3⇒1⇒2の順がおすすめ。
コツコツ進むならパート1⇒2⇒3の順がおすすめ。

詳しく説明いたします。
CIAのパート構成
CIAの資格試験は3つのパートから成っています。期間内に3つとも受かれば資格取得となります。
それぞれのパートの概要は以下の通りです。
CIA パート1 ー 内部監査に不可欠な要素
CIA パート2 ー 内部監査の実務
CIA パート3 ー 内部監査のためのビジネス知識
http://www.iiajapan.com/pdf/certifications/info/CIA-Exam-Syllabi-Changes-Handbook-Japanese.pdf
予備校のテキストのページ数や私が費やした時間に基づく、それぞれのパートのボリュームは以下の通りです。
- パート1-ボリューム:小
- パート2-ボリューム:小
- パート3-ボリューム:大(パート1またはパート2の約2倍)
(参考)
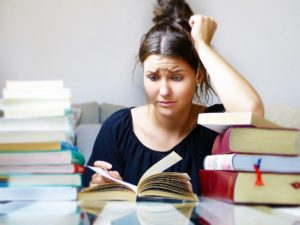
パートごとの相関関係(パートをまたがって出題されるケース)について
試験ではそれぞれのパートが完全に独立して出題されるわけではなく、パートにまたがって出題されることがあります。
相関関係は以下の通りです。
- パート1・・・パート2の学習分野から出題がされることがある。パート3の学習分野からの出題はない。
- パート2・・・パート1の学習分野から出題がされることがある。パート3での学習分野の理解を前提とした応用問題が出題されることがある。
- パート3・・・パート1およびパート2の学習分野からの出題はない。
以上から、以下のことが言えます。
- パート1とパート2とはひとまとめにして学習したほうが効率的である。
- パート2は、パート3の学習分野を理解しておくことで試験対策上有利になる。
- パート3は、独立した学習で合格を狙える。
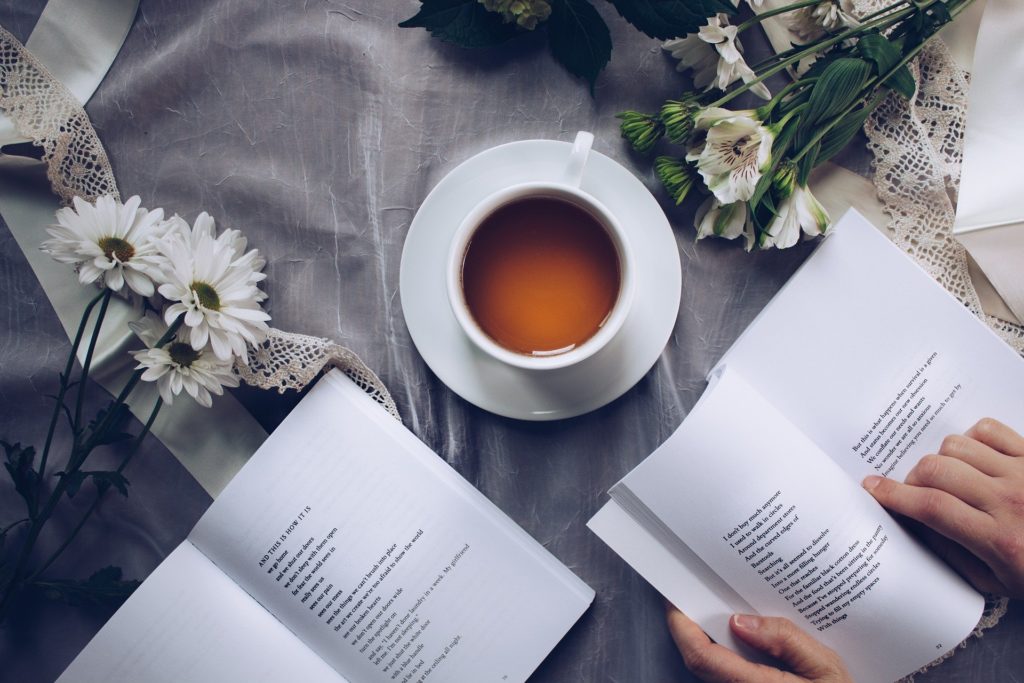
「最短合格をめざすならパート3⇒1⇒2の順がおすすめ」な理由
なぜパート3を最初に学習・受験することをおすすめするのかというと、パート3は、ほかのパートとの相関関係がないため、単独の学習で合格を狙うことができるからです。
また、パート3を学習することは、パート2の応用問題の対策にもなります。(パート3の勉強をしないままパート2の試験を受けると不合格のリスクが高まります)
よって、パート3⇒1⇒2(パート1とパート2はひとまとめにして学習)の順で学習・受験するのが、それぞれのパートの一発合格を狙える順序だと言えます。
この順序のデメリットは、先にボリュームの大きいパート3を学習することの心理的なハードルの高さ、ストレスの大きさだといえます。(パート3は、「ミニMBA」とも言われ、幅広いビジネス関連の知識の習得が求められます)
CIA合格のためには、どのパートもいつかは勉強し、合格しなければなりませんので、割り切ってパート3を最初に勉強するのも一つの策といえます。
「コツコツ進むならパート1⇒2⇒3の順がおすすめ」な理由
イメージで言いますと、基礎(パート1)⇒応用(パート2)⇒関連知識(パート3)と、順序だった学習が可能ですので、内部監査に関する予備知識のない方がコツコツと学習し、合格を狙うのであれば、こちらがおすすめです。
最初はやさしいので、勉強のモチベーションも続きます。
しかしながら、この順序のデメリットは、「パート2の不合格のリスクが高くなること」です。
実際、私はこの順序で学習し、パート1は一発合格できたものの、パート2の一回目の受験は不合格でした。
パート2の不合格後、専門校(アビタス)のアドバイザーの方に再受験対策の相談をしました。
その方からは「パート2の勉強をやりなおすのではなく、パート3の勉強を始めてみてはどうか」というアドバイスをいただきました。
そのアドバイスにしたがい、パート3の学習を開始しました。また、試験の順番を変え、パート2の再受験を後回しにして、先にパート3の受験をしました。(パート3の結果は合格)
その後、パート2を再受験し、こちらも合格できました。
パート3の財務・会計の知識をベースとした、パート2の応用問題にも対応できた実感がありました。
このように、順序だった学習が可能であるものの、パート2の不合格のリスクが高くなることで、全科目の合格が遠回りになる可能性があるのがこの順番です。
アビタスのアドバイザーの助言にも助けられました。


(参考)すべてのパートを一気に学習する方法
上記以外に、「すべてのパートを一気に学習する方法」が紹介されているのを見たことがあります。
この方法であれば、全体像をつかむことでパート間の相関関係の問題もクリアになりますので、最短で全科目合格を狙えるかもしれません。
しかしながら、この方法の弱点は、「覚えたことを忘れてしまうこと」と「試験に向けたモチベーションが薄れしまう」ことだと思います。
すべてのパートをひと通り勉強しおわるころには最初に学習したことを忘れてしまうリスクが高まりますし、試験というイベントが前述の2つの順序に比べて先送りされますので、試験に向けた集中力、緊張感が損なわれるかもしれません。
したがって、私はこの方法はおすすめしません。

最後におさらいをさせてください。
- 最短合格をめざすなら、パート3⇒1⇒2の順がおすすめ
- コツコツ進むなら、パート1⇒2⇒3の順がおすすめ
です。

私自身も、CIA試験対策に関する情報が限られていた中、ほかの受験者の方の勉強方法や受験の順番を参考にしました。
皆さんに合った学習プランを見つけることのお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
あわせて読みたい
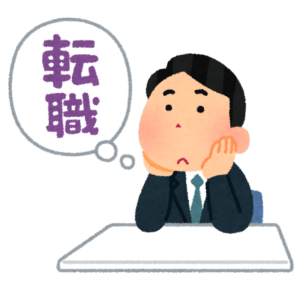









コメント